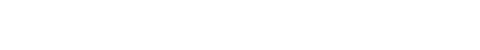「1学期終業式」 7月19日
1年生の育てた朝顔が色鮮やかに咲いています。今日で81日間の1学期が終わります。
体育館で終業式が行われました。その中で、校長先生が、「二つのやくそく〈早寝・早起き・朝ごはん〉〈よく学び、よく遊ぶ〉を実行しましょう。」とお話しされました。規則正しい生活を送り、興味あることを深く勉強して時間を大切に使いましょう。
学年代表による「1学期を振り返って」の発表もありました。教科学習では、あきらめずに最後までがんばることの大切さに気付いたり、グループの話合い活動では、我を通すことよりも目的を明確にし、譲ることが効率的であるということに気付いたり、それぞれの成長が感じられました。友達の発表に真剣に聞き入る子ども達は、どんな想いをもったでしょうか。
2学期には、元気に日焼けした顔がそろうといいですね。楽しい夏休みを!
 |
 |
 |
 |